3. カリキュラムの魅力
実際の授業内容やロボットの制作例
ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室の最大の特長のひとつが、毎月異なるロボットを自分の手で組み立てる、実践型のカリキュラムです。
子どもたちは、完成を目指して夢中で作業に取り組む中で、自然と論理的思考力や創造力、問題解決力を身につけていきます。
ここでは、実際の授業の進め方や、制作するロボットの一例をご紹介します。
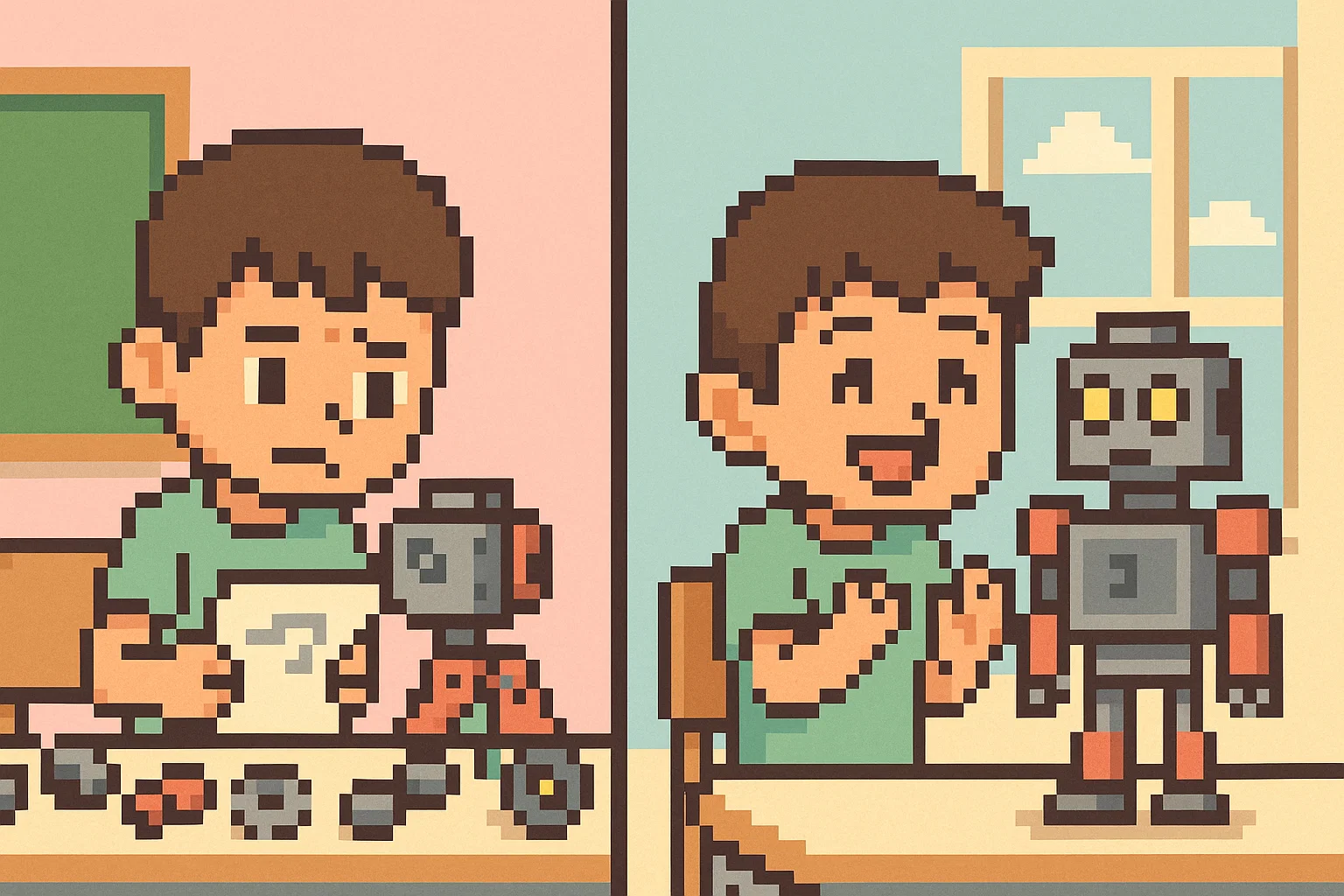
授業の基本構成(各月2回・90分)
ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室では、1ヶ月に2回(1回約90分)の授業で、1体のロボットを完成させるカリキュラムが組まれています。各月の授業は以下のように進行します。
【第1回】ロボットの基本組み立て
– 教材テキストを見ながら、指導を受けつつロボットを一から組み立て
– モーターやギア、リンク機構の使い方を実践的に学ぶ
– 組み立て後、実際に動かしてチェック
【第2回】改造・応用・自由発想
– 組み立てたロボットに独自の改造を加える
– 「もっと速く動かすには?」「違う動作をさせるには?」といった課題に挑戦
– 発表やプレゼンの時間がある教室もあり、表現力も育成
この構成により、設計・構築・評価・改善というエンジニアリングサイクルを子どもたちが体験できるのです。
制作するロボットの一例(コース別)
コースごとに子どもの発達段階に応じた難易度・構造のロボットが用意されています。
プレプライマリーの制作例
– ブランコロボ ゆらリン:ブランコがテーマのロボットです。
– はいたつロボ モッテクテク:物を置かれたら自動で運ぶロボットです。
プライマリーの制作例
– カブトムシロボット メカビートル:カブトムシの角の根本部分にタッチセンサーを取り付けてあり、テーブルの端を検知して自動停止します。
– 蒸気機関車ロボット SLロボロコ:蒸気機関車(SL:Steam Locomotive)のピストンの動きを再現したロボットです。
ベーシックコースの制作例
– 一本勝負! ケンドーロボ:相手を見つけると竹刀を振る剣道ロボットです。
– おそうじロボット ロボクリーン:先端のローラー部分のパーツが回転し、小さな物を拾い集める掃除機ロボットです。
ミドルコースの制作例
– つかんでゲット! ロボキャッチ:モーターの正転・逆転だけで、「レールの上を移動する」、「ものをつかむ」、「ものをはなす」という動作ができるロボットです。
– 水辺の王者 ロボゲーター:前後の足の動きに合わせて、しっぽを左右に振りながら前進する、ワニ型ロボットです。
アドバンスコースの制作例
– 演奏ロボ ドレミボット:2つのモーターを使い、腕を振る動作で木琴の演奏を再現しています。
– 二足歩行ロボ アルクンダーZ:左右の重心移動しながら二足歩行するロボットです。
教材も一流、わかりやすさに配慮
– 写真や図解が豊富なテキストで、低学年の子どもでも直感的に理解可能
– 各パーツの名称・機能を学ぶミニ解説付きで、自然と「工学リテラシー」も身につく
– 毎月違うテーマで飽きずに学べる内容設計
子どもたちの反応・学びの深まり
保護者やインストラクターからも、以下のような声が多く寄せられています。
>「初めは組み立てだけだったのが、今では改造アイデアを自分から出すように」
>「“なぜうまく動かないのか”を自分で考えられるようになった」
>「発表で人前でも堂々と話せるようになった」
こうした変化は、子ども自身の“考える力”と“自己表現力”の育ちを物語っています。
プログラミングや論理的思考をどう育むのか?
ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室では、ロボット制作の過程を通じて、子どもたちが自然とプログラミング的思考や論理的思考力を身につけられるよう、段階的なカリキュラムが構成されています。これは、教科書的な学びではなく、「体験しながら学ぶ」ことを重視した教育設計です。

組み立てと動作のしくみから論理的思考を引き出す
ロボット教室で最初に行うのは、設計図を見ながらブロックやモーター、ギアなどを組み立てていく作業です。このとき、子どもたちはただの工作ではなく、「なぜこのギアをここに付けるのか」「このモーターはどこに接続すれば動くのか」といった因果関係や手順の理解を求められます。
動作確認の段階で思い通りに動かないこともありますが、ここからが学びの本番です。「どこが間違っているのか」「どうすれば改善できるのか」を自分なりに考え、改良していく中で、論理的に物事を考える力が養われます。
このようにして、ロボットを作る一連のプロセスの中で、子どもたちは物事を順序立てて考え、目的達成までの手順を組み立てる力=論理的思考力を自然に習得していきます。
プログラミング的思考の基礎を体験的に習得
ロボット制作の改造や応用では、「こうしたらこう動く」という試行錯誤が求められます。これはまさに、現代の教育で重要視されているプログラミング的思考のトレーニングと重なります。
プログラミング的思考とは、目的達成のために必要な手順や条件を整理し、効率的な順序で物事を進める力のことです。ロボット教室では以下のような形でこの力を育みます。
– 命令の順序を考える(アルゴリズム)
– 条件によって動きを分ける(条件分岐)
– 同じ動作を繰り返す(ループ処理)
– トラブル時に原因を特定し、修正する(デバッグ)
こうした要素は、初級の段階では視覚的な組み立てを通して、上級になるとプログラミングソフトを使ってより本格的に学習します。
アドバンスコースでのプログラミング学習
ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室のアドバンスプログラミングコースでは、ビジュアルプログラミングによる本格的なロボット制御に取り組みます。
ビジュアルプログラミングとは、命令ブロックをドラッグ&ドロップで組み合わせていくもので、コードを書く必要がなく、直感的に理解できるのが特徴です。この形式により、プログラミングが初めての子どもでも、複雑な命令や制御を楽しく学ぶことができます。
さらに、光センサーや距離センサーを活用して、状況に応じた動作をプログラムすることで、より実践的なプログラミングスキルとともに、判断力や論理の構造化能力が身についていきます。
問題解決力と考える習慣が定着する
ロボットがうまく動かない、想定した通りに制御できないという体験は、単なる「失敗」ではなく、新たな気づきと学びの機会になります。自ら課題を発見し、仮説を立て、修正を重ねて再挑戦する。その一連の流れが、問題解決力と自発的な思考習慣を育てる土台となります。
この「考える→試す→直す」という習慣は、将来的にどんな分野に進んでも活かせる汎用的な学力と言えるでしょう。
論理的思考とプログラミングの学びをつなぐ環境
ヒューマンアカデミーでは、すべてのコースにおいて、「なぜそうなるのか」「どうすればうまくいくのか」を重視する探究型学習の姿勢が一貫しています。
この姿勢が、論理的思考とプログラミングの学びを自然につなげ、子どもたちが自らの力で考え、工夫し、成長していく力を支えているのです。
教材やサポート体制の紹介
ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室では、子どもたちが楽しみながら本格的なものづくりに取り組めるように、安全性・教育効果・創造性を兼ね備えた専用のロボット教材と、充実したサポート体制が整えられています。
この章では、実際に使用されている教材と、子どもたちの学びを支える教室・家庭でのサポート体制をご紹介します。
正確な教材パーツ構成
ヒューマンアカデミーのロボット教材は、子ども向けでありながら、本物のロボットに近い構造の理解ができるよう設計されています。工具を使わず、手で組み立てることができる安全性と、繰り返し使える耐久性も兼ね備えています。
主に使用されているパーツ(公式パーツガイド準拠):
– シャフト:動力をタイヤやギアに伝える回転軸。ロボットの“動き”の基本を担う重要パーツ。
– ペグ:他のパーツをつなぐ接続部品。ビームやロッドの組み立てに不可欠。
– ブッシュ:パーツの位置調整や固定に使用。構造の安定性を支える。
– ビーム:ロボットのフレームとなる棒状のパーツ。長さ・形のバリエーションがあり、設計の自由度を広げる。
– ロッド:リンク機構や可動部分の再現に使用。動きに連動を持たせる際に活用。
– ギア:回転や速度の変化を学ぶための歯車。ギア比の理解にも活用される。
– モーター:ロボットの駆動部。電気エネルギーを動力に変え、動作を実現する。
これらのパーツは、単に「組み立てる」だけではなく、動きの仕組み・構造理解・応用力の育成といった学びの基盤となります。
年齢や発達段階に応じたテキストの工夫
ロボットの教材とあわせて使用されるテキスト(組み立てガイド)も、各コース・年齢に応じた工夫が盛り込まれています。
特にプレプライマリー・プライマリーコースでは:
– ひらがな中心の文章構成(漢字・カタカナにはふりがな付き)
– 実物大のパーツ写真を掲載し、どの部品を使うのか一目でわかる
– 作業手順が大きな図解と番号で示され、子ども一人でも読み進めやすい
– 各工程にわかりやすい注意書きや応援メッセージが添えられている
このような配慮により、子どもたちは「自分で読んで、自分でできた!」という自立した学びの体験ができます。
教室でのサポート体制
ヒューマンアカデミーでは、教材の質だけでなく、教室での指導の質にも徹底的にこだわっています。全国に展開する2,000以上の教室で、以下のような体制が整えられています。
主な教室サポート:
– 少人数制クラスで、講師が一人ひとりの様子をしっかり見守る
– 子どもの疑問や工夫に寄り添う声かけと支援
– 完成後の改造時間を設け、自分のアイデアをカタチにする体験を促進
– 発表や成果報告の機会を通じて、表現力や自信の育成にも配慮
指導にあたるインストラクターは、ヒューマンアカデミーの研修を受講・修了した認定インストラクターで、ロボットの知識だけでなく、子どもとの関わり方や学びの導き方に熟知しています。
家庭学習のサポート
ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室では、教室での学びを家庭にも広げられるよう、以下のような家庭向けのサポート体制も用意されています。
– 持ち帰り可能なロボットとテキストで、自宅でも復習や改造が可能
– 保護者向けに学習進捗のフィードバックを提供(教室による)
– 年度途中の相談やステップアップの個別アドバイス対応
親子で一緒にロボットの仕組みを話し合ったり、発表の練習をしたりすることで、家庭内でも学びとコミュニケーションが自然に育まれる環境が整っています。
まとめ
ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室の教材は、シャフト・ギア・ビームなど本格的なパーツを使いながらも、安全で扱いやすく、子どもたちの成長をしっかり支える設計になっています。
そこに、わかりやすいテキストと、インストラクターによるていねいなサポートが加わることで、「わかる」「できた」「もっとやりたい」が連続する学びのサイクルが生まれます。
この環境の中で、子どもたちは確かな技術力だけでなく、自信・創造力・思考力という未来を生き抜く力を身につけていくのです。

